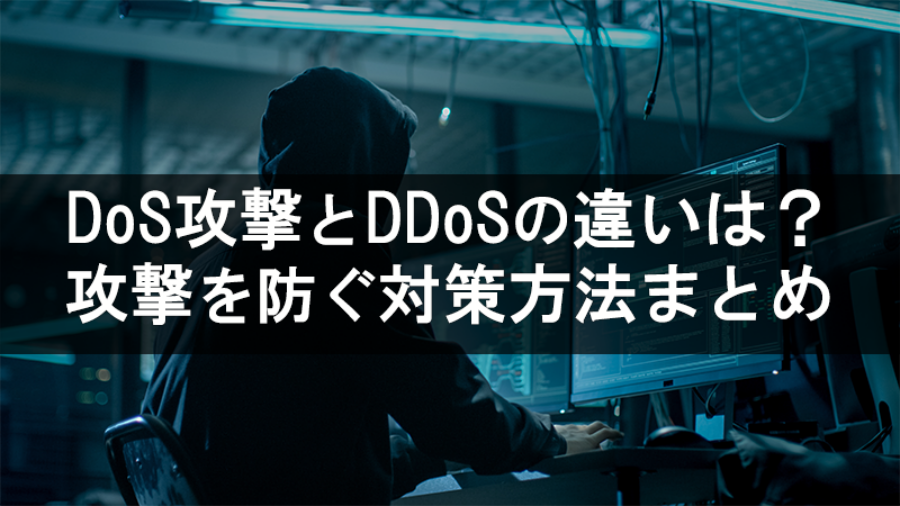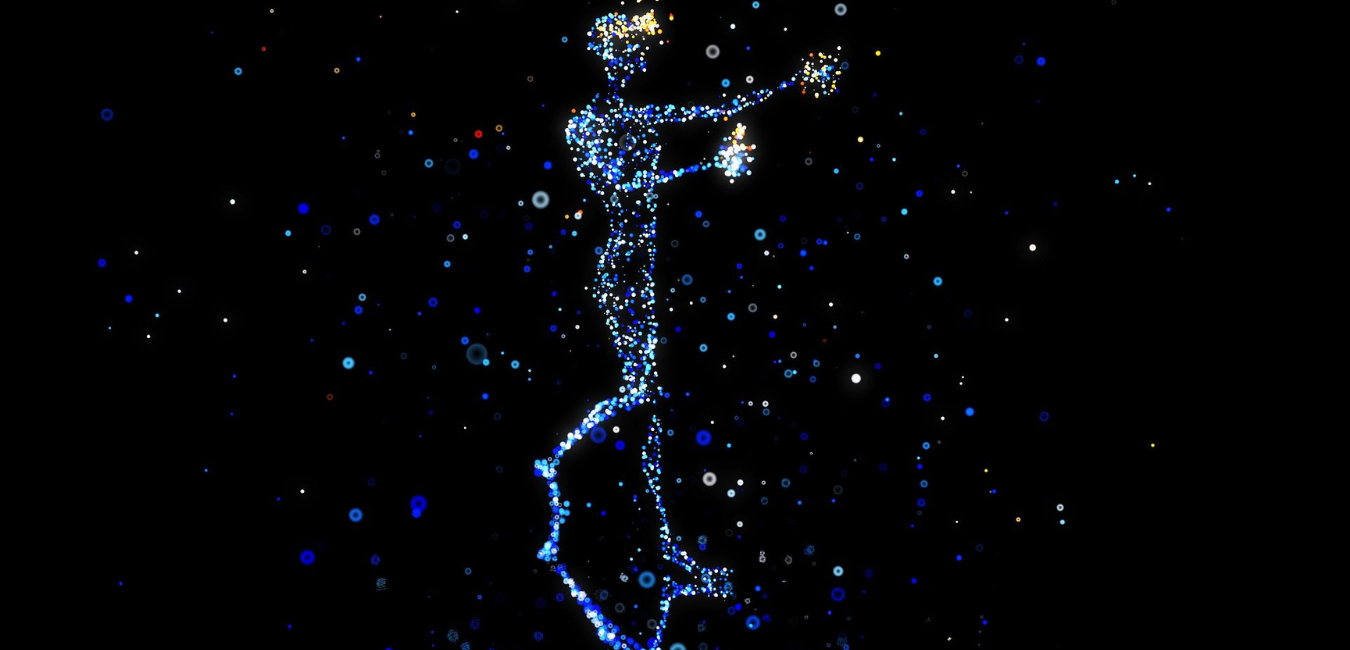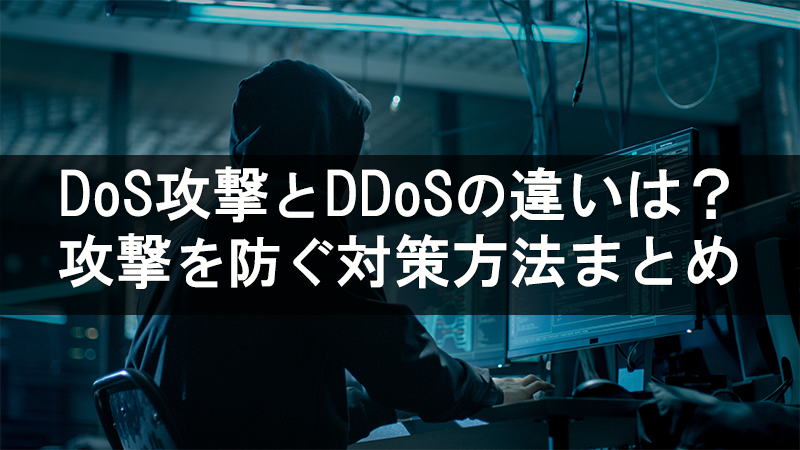
サイバー攻撃にはさまざまな種類があり、なかでもDoS攻撃やDDoS攻撃はよく知られた手法です。どちらも、ターゲットになると甚大な被害を受けかねないので、企業は適切な対策を行わねばなりません。
本記事では、DoS攻撃とDDoS攻撃の概要やそれぞれの違いなどを解説します。併せて、具体的な対策方法についてもお伝えするので、今からでも対策への取り組みを始めましょう。
DoS攻撃とは?
DoS攻撃(Denial of Service Attack)とは、特定のWebサイトやアプリへ意図的に負荷をかけるサイバー攻撃の一種です。1台の端末から大量のデータを送ることでサーバーに負荷をかけ、機能障害を引き起こします。
DoS攻撃のターゲットとなるのは、規模の大きなWebサイトばかりではありません。個人サイトや知名度が低いアプリであっても狙われることがあるため注意が必要です。
DoS攻撃の種類としては、通常を装って短時間に大量のアクセスを行う「フラッド(洪水)型」と、サーバーの脆弱性をついて膨大な処理を行わせたり、マルウェア感染を狙う「脆弱性型攻撃」の2つが代表的です。
DDoS攻撃とは?
DDoS攻撃(Distributed Denial of Service Attack)は、DoS攻撃をさらに強力にしたサイバー攻撃です。DoS攻撃が1台の端末から仕掛けるのに対し、DDoS攻撃は複数の端末からターゲットのサーバーへ負荷をかけます。
DDoS攻撃の特徴は、事前にマルウェアなどを用いて乗っ取った端末を攻撃に使うことが多い点です。マルウェアに感染した不特定多数の端末へ攻撃者が命令を出すと、ターゲットに対し一斉に攻撃を加えます。
なお、乗っ取られた端末の所有者が攻撃に気づきにくいことも、DDoS攻撃のおそろしいところです。特定のWebサイトを攻撃する意思などなくても、知らぬうちにDDoS攻撃に加担させられることがあります。
DoS攻撃とDDoS攻撃の違い
DoS攻撃とDDoS攻撃は、どちらもサーバーに大量のデータを送り、負荷をかけて機能障害へ追い込む手法です。
双方では、攻撃を仕掛ける端末の数に違いがあります。DoS攻撃は1台の端末で実行されますが、DDoS攻撃では複数の端末が使われます。
複数の端末で大規模な攻撃を行うDDoS攻撃は、1台のみのDoS攻撃より被害が大きくなりがちです。また、DDoS攻撃の多くはマルウェアなどで乗っ取った端末を用いることから、攻撃者が直接的に行うDoS攻撃と比べて攻撃元の特定が難しい点にも違いがあります。
・攻撃を行う理由・目的
これらの攻撃を行う目的のひとつとして、ターゲット企業のイメージダウンが挙げられます。サーバーに高負荷がかかると、機能障害によってユーザーがアプリやECサイトなどのWebサービスを利用できない、という状況に陥りかねません。被害を受けた企業は、セキュリティ対策が弱い、サービスが不安定で信頼性に欠ける、といったネガティブな印象をユーザーに与えます。
また、嫌がらせやいたずら、脅迫、抗議などを目的とすることがあります。「楽しいから」「困った様子を見てみたい」といった愉快犯的な犯行のほか、「金銭を支払えば攻撃を停止する」という脅迫などのために行われます。
DoS攻撃・DDoS攻撃で起こりうる被害とは?
DoS攻撃やDDoS攻撃によって、金銭的な被害を受けるおそれがあります。たとえば、ゲームアプリを運営している企業であれば、攻撃によって一時的に障害が発生すると、ユーザーがアイテムを買えない状況に陥るかもしれません。
このようなサービス・商品の販売機会の損失に加えて、不具合が発生する、一部サービスを利用できないといった機能不全の結果、ユーザー離れを招くおそれもあります。
ほかにも、サーバーに負荷がかかることで通常業務に支障をきたすかもしれません。業務が停止、混乱するほどの被害を受けた場合、原因究明や復旧までに時間がかかれば、その間に得られたはずの利益分の損害が発生します。
DoS攻撃・DDoS攻撃の対策方法3選
DoS攻撃やDDoS攻撃は、適切な対策によって防御が可能です。具体的な対策としては、同一IPや海外からのアクセス制限、対策サービスの導入、OSやアプリの常時最新化の3つです。
1.同一IP・海外からのアクセスを制限する
PCやスマートフォンといったネットワーク機器には、各端末を識別するためのIPアドレスが割り当てられています。
同じIPアドレスの端末からしつこく攻撃を受けているようなケースでは、特定のIPアドレスのアクセスを制限することで対策できます。なお、この方法はひとつのIPアドレスを使用するDoS攻撃に対しては有効ですが、多数の端末を用いるDDoS攻撃にはあまり効果がありません。
ほかには、アクセス分析して海外の一部の国から攻撃が多いと分かれば、その範囲でアクセス制限を実施するのも手です。ただし、グローバルに展開するサービスでは、アクセス制限した国や地域への提供ができなくなります。そのため、この方法は国内向けに限るようなサービスで有効です。
2.DoS攻撃・DDoS攻撃対策サービスを導入する
DoS攻撃やDDoS攻撃は、専用の防御サービスの導入によって対策が可能です。代表的なサービスとしては、WAFやUTMなどが挙げられます。
WAF(Web Application Firewall)は、Webサイトの保護に特化したセキュリティソリューションです。不正アクセスの検知機能によって、一般的な利用とDoS攻撃・DDoS攻撃を見分け、攻撃のみを止められます。ほかにも情報の搾取やシステム基盤の侵害といった脅威度の高い攻撃からWebサイトを守ります。
UTM(Unified Threat Management)は、日本語で統合型脅威管理と訳されます。コンピュータやネットワークを、外部からの脅威から守る管理手法のことです。ファイアウォールやIPS、アンチスパムなどのセキュリティツールを統合することで、効率的なセキュリティ強化を実現します。
DDos攻撃への対策としてCloudbric ADDoSがあります。Cloudbric ADDoSはDDoS攻撃の防御に特化したクラウド型セキュリティサービスです。全世界に分散配置したエッジネットワークを利用し、最大100Tbpsの大規模攻撃まで防御が可能です。
参考:Cloudbric ADDoS
3.OSやアプリを最新版に保つ
DoS攻撃・DDoS攻撃は、単純にアクセスを繰り返すだけでなく、セキュリティ対策を潜り抜けてアクセスを確立させられるよう、年々手口を巧妙化させています。一方で、OSやアプリもそれに対応し、見つかった脆弱性をカバーするために更新され続けます。
OSやアプリのバージョンが古いままでは、新たな攻撃手法に対応できず被害を受けるおそれがあります。こうしたリスクを軽減するため、OSやアプリは常に最新の状態で使用しましょう。定期的にアップデートを行い、最新の状態に保つことで攻撃を対策できます。
まとめ
DoS攻撃とDDoS攻撃は、どちらもターゲットのサーバーに過度な負荷をかけ、機能障害などを引き起こすサイバー攻撃の手口です。機会損失に伴う金銭的な被害をはじめ、顧客離れにもつながるため、企業には適切な対策が求められます。
具体的には、攻撃対策サービスの導入、OSやアプリを最新の状態で使用するなどの方法が有効です。これらの対策により、脅威から組織を守れる環境を整えましょう。
Cloudbric ADDoSは全世界70以上のエッジロケーションを活用した高度化されたDDos攻撃防御サービスです。常時トラフィックの監視がリアルタイムに行われ、発信元に近いエッジにて攻撃を分散処理することで、最大100Tbps以上のトラフィックを緩和することができます。詳細は以下のサービス概要をご確認ください。
参考:Cloudbric ADDoS
▼製品・サービスに関するお問い合わせはこちら
▼Cloudbirc WAF+の無償トライアルはこちら
▼パートナー制度のお問い合わせはこちら