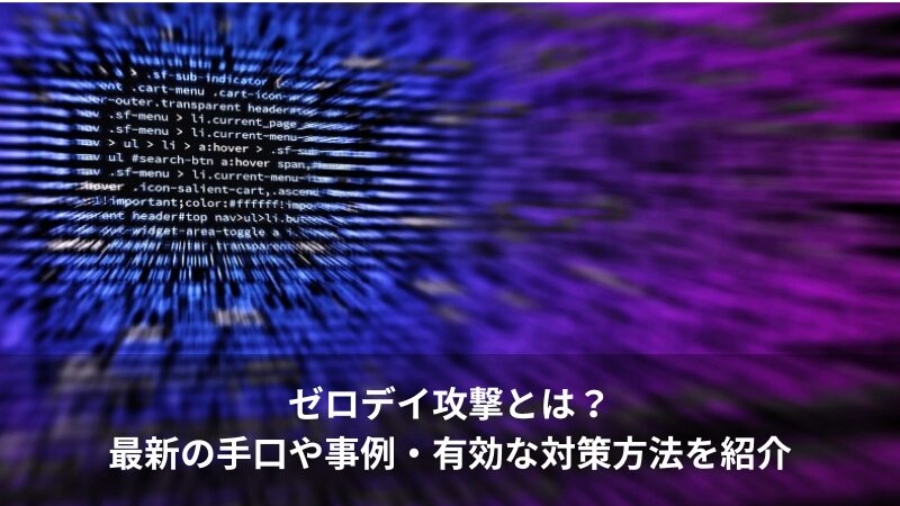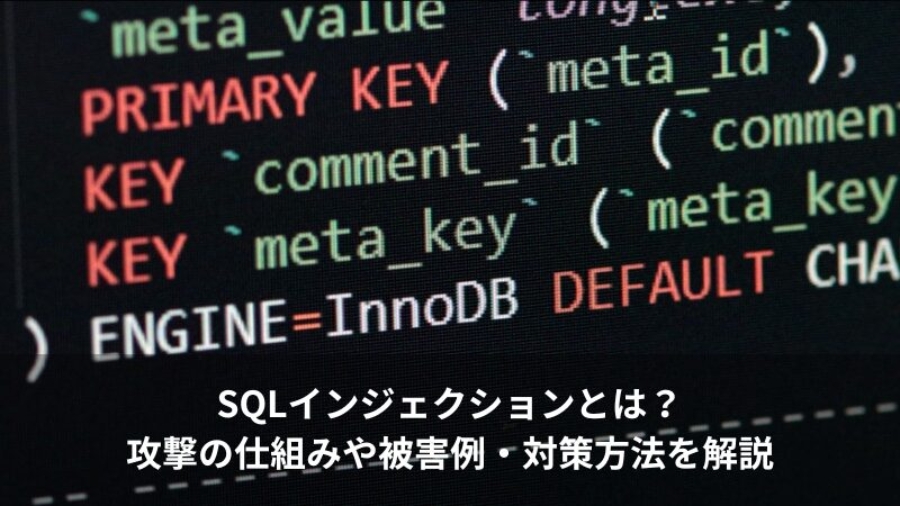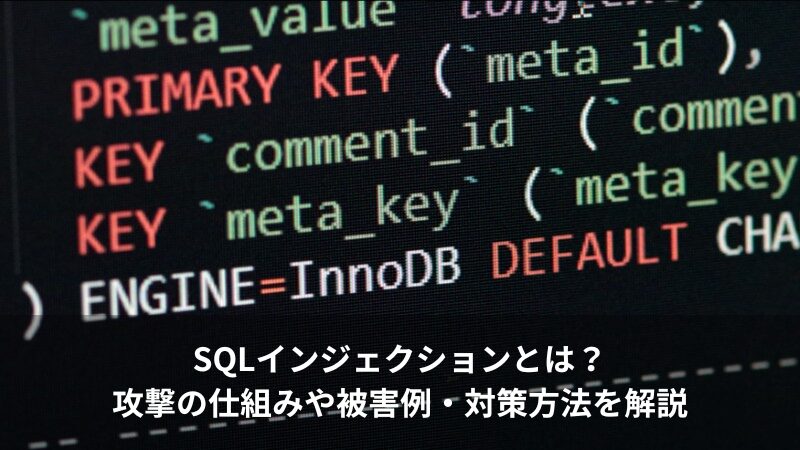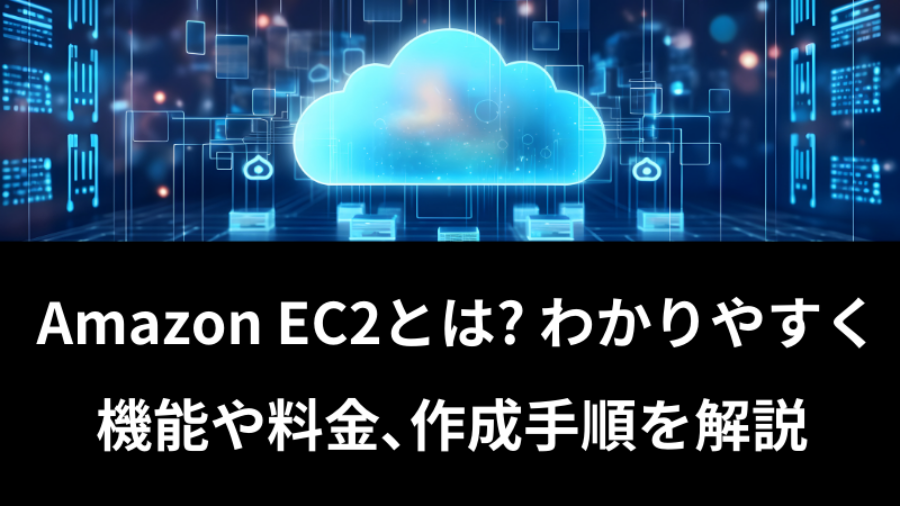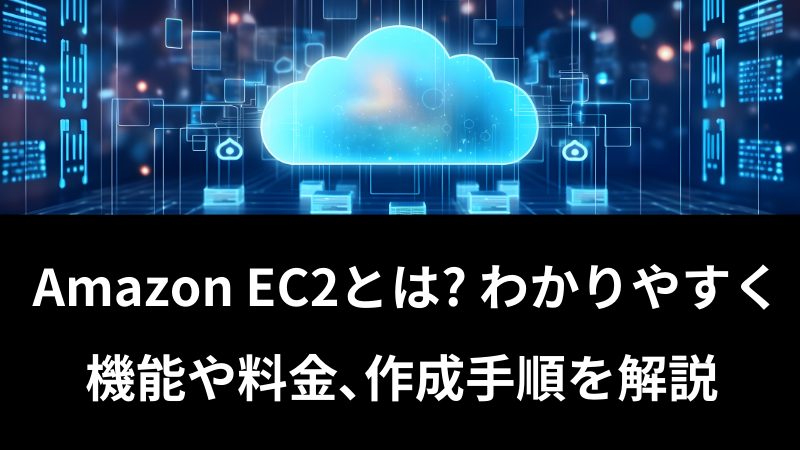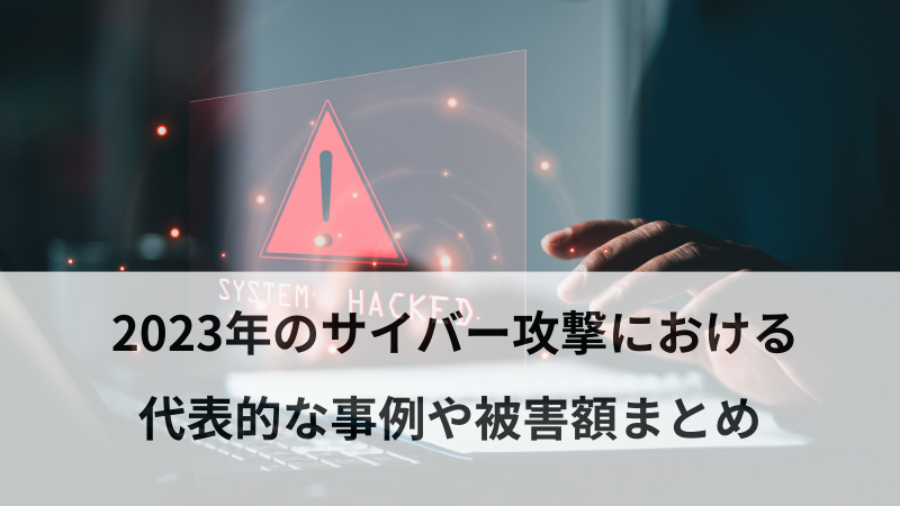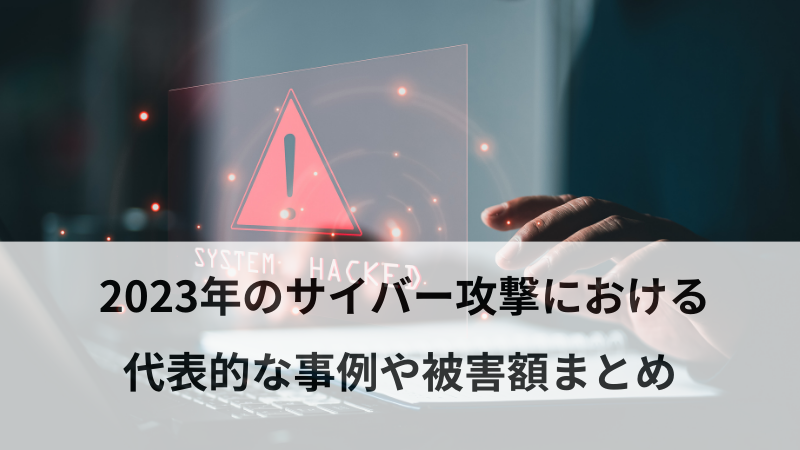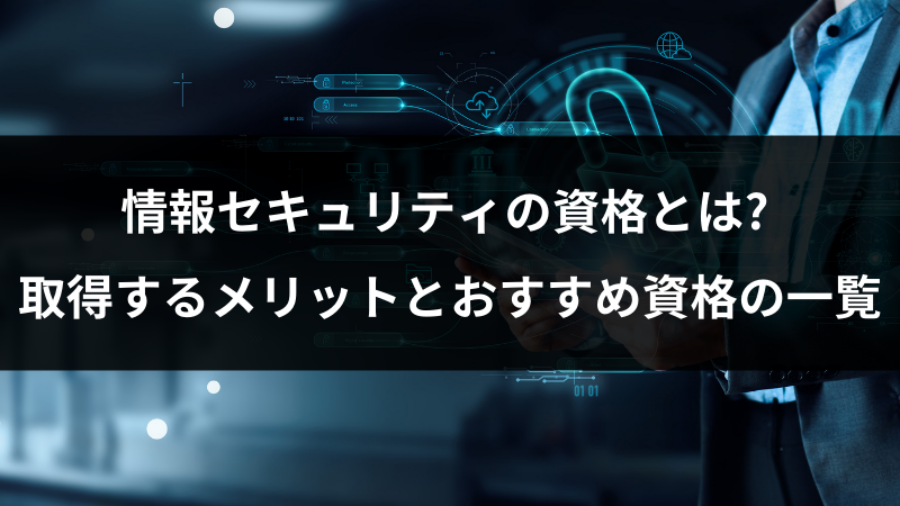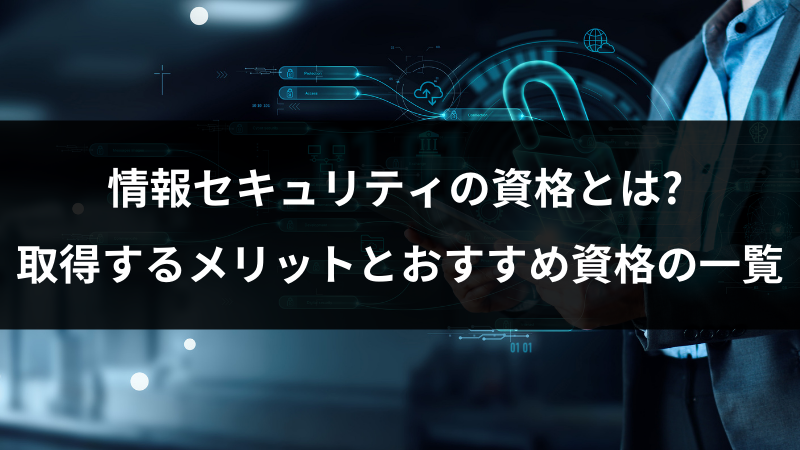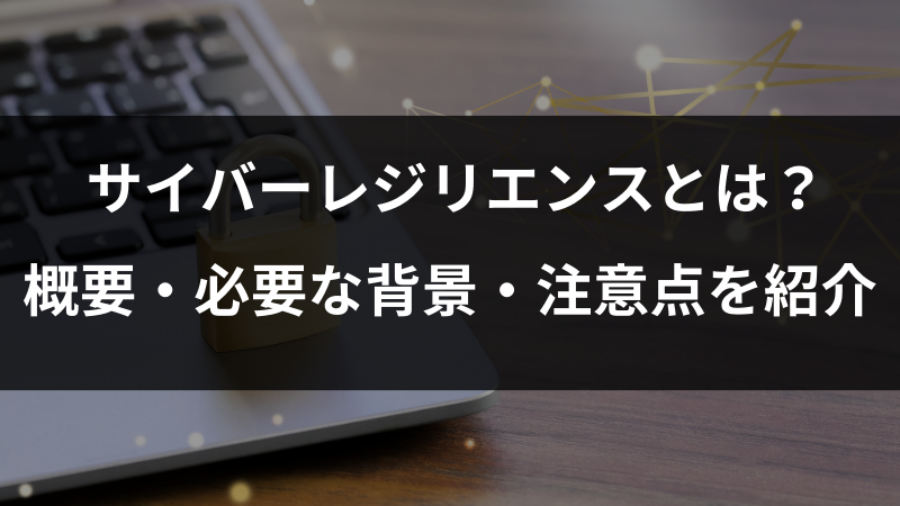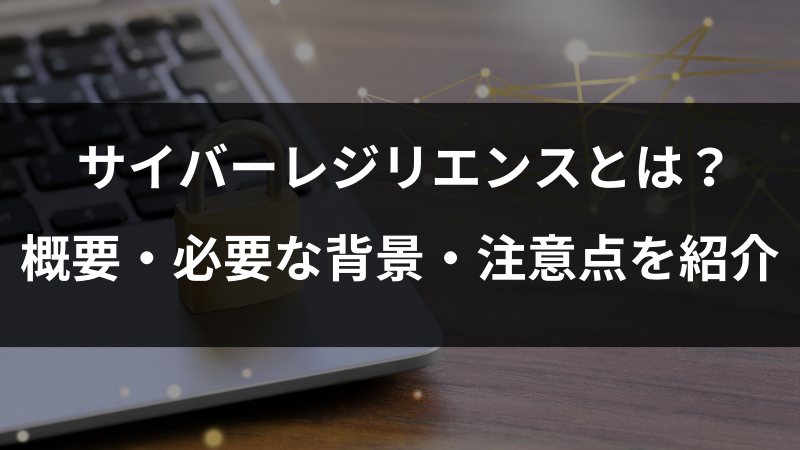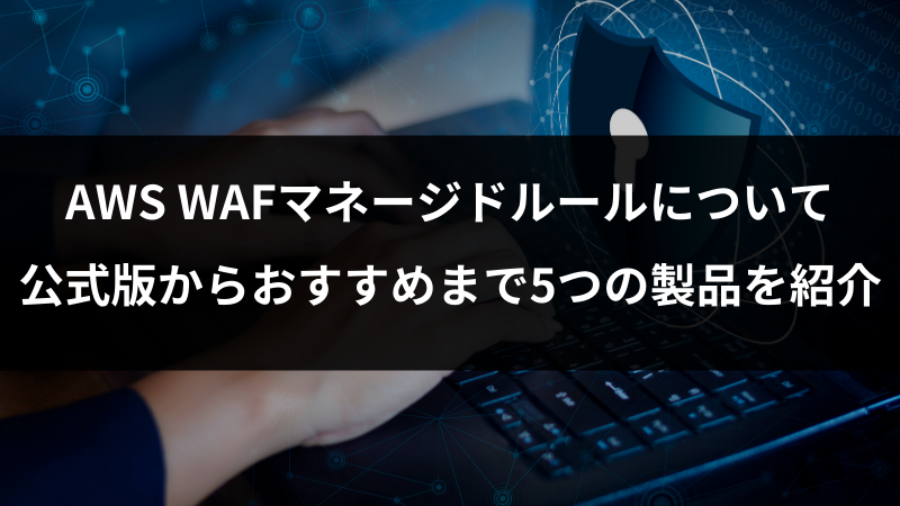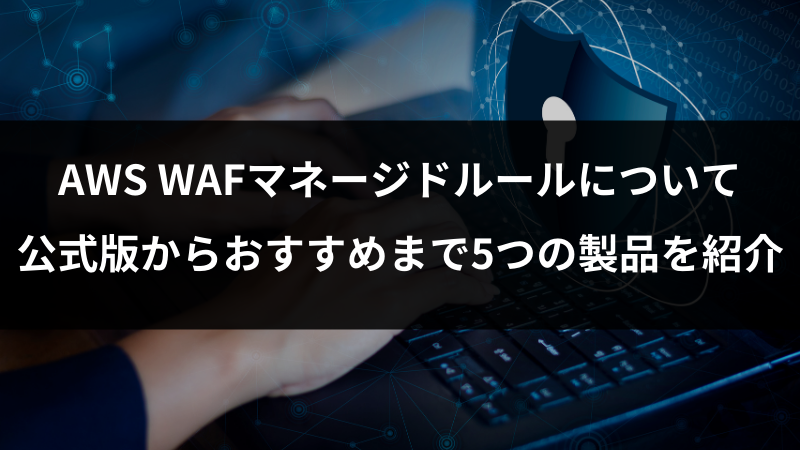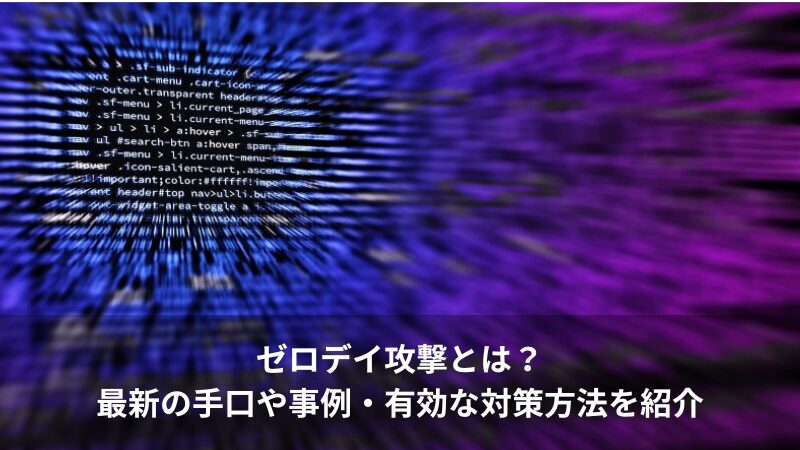
企業や個人を狙ったサイバー攻撃の中でも、とくに検知が難しく、深刻な被害をもたらすもののひとつが「ゼロデイ攻撃」です。ソフトウェアの不具合を突く手口は年々巧妙化しており、最新のセキュリティ対策を講じていても、完全な防御は困難とされています。
この記事では、ゼロデイ攻撃の基本から主な手法、実際の被害事例、そして有効とされる多層的な対策手段を紹介します。
ゼロデイ攻撃とは?
「ゼロデイ攻撃」とは、ソフトウェアの欠陥(脆弱性)が発見され、修正プログラム(セキュリティパッチ)が提供される前に、その隙を突いて行われるサイバー攻撃のことです。
脆弱性は設計上のミスや不具合に起因し、攻撃者に悪用されると情報漏えいや不正侵入などの被害が生じることがあります。パッチ適用までの「ゼロ日間」を狙うことから、この名が付けられています。
Nデイ攻撃との違い
ゼロデイ攻撃に似た手口として「Nデイ攻撃」があります。これは、すでに公開されている対策用のパッチの脆弱性を狙うサイバー攻撃です。ゼロデイ攻撃ほど高度な技術は必要とされず、インターネット上に概念実証コード(PoC)や攻撃に使えるツールが出回っているため、攻撃者にとって扱いやすい点が特徴です。
対策が遅れると、情報漏えいやデータ改ざん、システム破壊など深刻な被害に発展するリスクが高くなるため、十分な注意が必要とされています。
ゼロデイ攻撃の主な手法
ゼロデイ攻撃にはさまざまな手法が存在します。ここでは、近年特に多く確認されている代表的な攻撃手口について解説します。
手法①メール
メールを使ったゼロデイ攻撃の手口として、業務連絡や請求書の通知を装い、マルウェアを含むファイルを送付するケースがあります。受信者が添付されたWordファイルやPDFを開くと、端末がウイルスに感染し、社内の情報が外部に漏れたり、不正にアクセスされたりする危険があります。
このような攻撃は、特定の企業や団体を狙う「標的型攻撃」と、不特定多数に同時に送信する「ばらまき型攻撃」に分けられます。実際に国内外の多くの企業が、業務を停止したり金銭的な損害を受けたりする被害を経験しています。
手法②Webページの改ざん
Webサイトの脆弱性を悪用する手口のひとつに、「Webページの改ざん」があります。この攻撃では、ページ内に悪意あるコードが埋め込まれ、訪問者が意図せずスクリプトを実行してしまう事態が発生します。
その結果、訪問者のパソコンにマルウェアが自動的にダウンロードされたり、入力された氏名や連絡先といった個人情報が盗まれたりする被害につながります。とくにアクセスが集中する人気サイトは狙われやすく、企業や団体には継続的な対策が求められます。
手法③Officeファイルを悪用
ゼロデイ攻撃では、WordやExcelなどのMicrosoft Officeファイルに仕込まれたマクロやスクリプトを利用して感染させる手法もあります。
受信者が何気なくファイルを開いた瞬間に悪意あるコードが実行され、マルウェアが自動的にダウンロードされます。こうしたファイルは、主にメールやSMSを通じて送りつけられ、情報漏えいや業務停止といった深刻なリスクを引き起こすこともあります。
手法④ツールの脆弱性を悪用
日ごろ業務で使われているツールやソフトウェアも、設計上の脆弱性を突かれると攻撃の入り口になります。ソフトの欠陥を狙うゼロデイ攻撃は、メールを使った手口と同様に、特定の対象を狙う「標的型」と、不特定多数に仕掛ける「ばらまき型」の両方が存在し、さまざまな組織に被害が広がっています。
最近では、セキュリティ対策の一環として使われているVPN製品に対する攻撃が増えています。警察庁の報告によれば、ランサムウェア感染の半数以上がVPNの脆弱性をきっかけに発生しています。
ゼロデイ攻撃の事例
過去、ゼロデイ攻撃による被害はどのようなものがあったのでしょうか。ここでは代表的な事例を3つ紹介します。
事例①Log4Shellの悪用
Log4Shellは、2021年11月に見つかったApache Log4j(Javaで開発されたアプリケーション向けのログ出力ライブラリ)の深刻な脆弱性で、危険度を示すCVSSスコアで最高の「10」が付けられました。
この問題が公表されてから、世界各地で数百万件の攻撃が確認され、1分間に100件を超える試行が行われたという報道もあります。Amazon、Google、Appleといった大手のクラウドサービスやアプリにも影響が及び、全体の4割を超える企業ネットワークが標的になったとされています。
事例②法人向けメールサービスで30万件超の情報漏えい
2025年4月、大手IT企業が提供する法人向けメールセキュリティサービスにおいて、約30万件を超えるメールアカウント情報が外部に漏えいしたことが判明しました。
原因は、当該サービスの導入時に利用されていたメール基盤の脆弱性が、ゼロデイ攻撃によって悪用されたことによるものでした。現在、同社では24時間体制のセキュリティ監視を強化するとともに、再発防止に向けたシステムの見直しを行っています。
事例③大手コーヒーチェーンのオンラインストアで情報漏えい
2024年5月、大手コーヒーチェーンのオンラインストアが不正アクセスを受け、個人情報やクレジットカード情報が流出する事件が発生しました。
漏えいしたのは、およそ9万人の登録情報と約5万人分のクレジットカード情報で、不正アクセスの原因はシステムの脆弱性によるものでした。さらに、ペイメントアプリケーションの改ざんも行われ、大規模な情報漏えいに発展したとみられています。
ゼロデイ攻撃への対策
ここではゼロデイ攻撃への3つの対策を紹介します。
対策①最新のセキュリティパッチの適用
ゼロデイ攻撃に対する最も有効な対策のひとつは、最新のセキュリティパッチを迅速かつ確実に適用することです。パッチの未適用は、既知の脆弱性をそのまま放置することになり、攻撃者に悪用されるリスクが高まります。
特に管理対象のソフトウェアや端末が多い場合は、専用のパッチ管理ツールを活用することで、適用状況の一元管理や可視化が可能となり、全体のセキュリティリスクを大幅に軽減できます。
対策②従業員へのセキュリティ教育
サイバー攻撃の多くは、操作ミスや油断といった人為的な隙を突いて行われます。そのため、従業員が日常的にセキュリティを意識しながら行動する姿勢が、組織全体の防御力を高めるうえで欠かせません。
定期的な社内研修やeラーニングを通じて、脅威に対する理解を深めるとともに、適切な対応力を身につけられます。教育の効果により、攻撃の兆候にも早く気づきやすくなり、万が一のインシデント発生時にも落ち着いて行動できるため、被害の拡大を防ぎやすくなります。
対策③セキュリティソフトやツールの活用
ゼロデイ攻撃に備えるうえでは、複数の対策を組み合わせた多層的な防御が効果的です。たとえば、ウイルス対策ソフトは既に知られているマルウェアへの対処に適していますが、未知の攻撃にはEDR(エンドポイントでの振る舞い検知)といったツールが有効です。
さらに、WAF(Webアプリケーションファイアウォール)を導入すれば、Webサイトへの不正アクセスや改ざんのリスクも抑えられます。最近では、ひとつのルールで数百の攻撃パターンに対応できる「ロジック型」の防御方法にも注目が集まっており、こうした複数の仕組みを適切に組み合わせることで、日々変化するサイバー攻撃への耐性を高める動きが広がっています。
ゼロデイ攻撃にはCloudbric WAF+で対策

ゼロデイ攻撃は、これまでのサイバー脅威とは性質が異なり、従来の対策の隙を突く高度な手法です。まだ発見されていない脆弱性を狙うため、決まった対策だけでは対応が難しくなります。企業は技術的なセキュリティ対策に加え、情報の取り扱いや社内体制の見直しにも取り組む必要があります。
ペンタセキュリティが提供するCloudbric WAF+は、クラウド経由で提供されるWAFであり、初めての方でも扱いやすい設計となっています。ゼロデイ攻撃を含む多様な脅威からWebサイトやアプリケーションを幅広く守る仕組みを備えています。
Cloudbric WAF+に関するご相談や詳細の確認をご希望の方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
クラウド型WAFサービス Cloudbric WAF+
▼WAFをはじめとする多彩な機能がひとつに。企業向けWebセキュリティ対策なら「Cloudbirc WAF+」
▼製品・サービスに関するお問い合わせはこちら